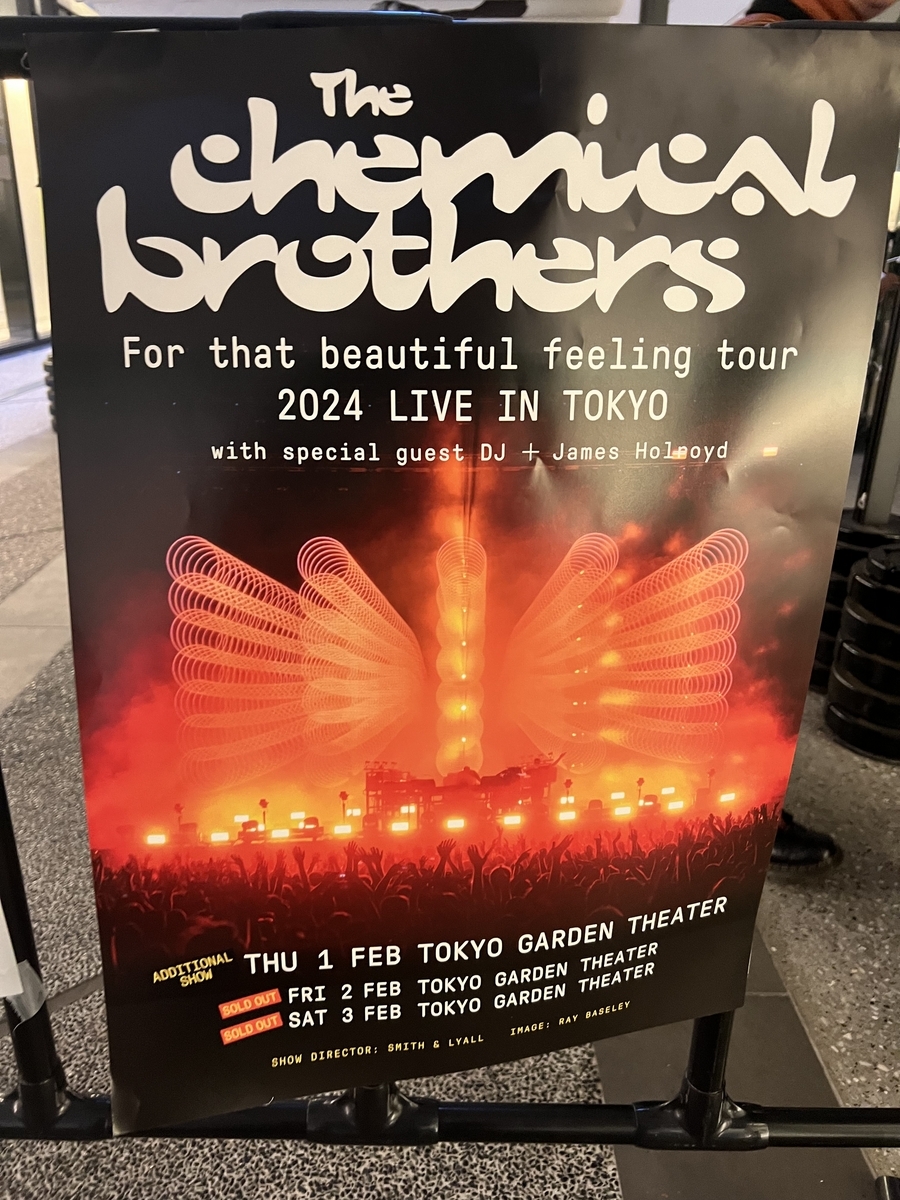読んで途中まで行った時、これはやられた、凄い本だなと思った。
本書は、当初、ハーバード大学出版から公刊され、2021年に著者による大幅な加筆改稿・再構成を経て、日本語で出版された。その後、多くの反響を呼び、第21回大佛次郎論壇賞(2021年)第75回毎日出版文化賞〔人文・社会部門〕(2021年)を受賞した。多くの書評もあるが、ここでは、中国プロパーの専門家として、津上俊哉氏のnoteを紹介しておく。
note.com
本書は、1946年9月2日のハワイから始まる、そして、戦後日本の「逆コース」、中華人民共和国成立前後の中国、韓国、フィリピンと移動し、そのローカルな歴史を、朝鮮戦争というグローバルな出来事につなぎ、再びローカルに戻り、冷戦とは何だったのかを鮮やかに明らかにする。
著者は冷戦とは何だったのかという問いに次のように答えている。すなわち、朝鮮戦争期に各地で同時発生した社会粛清運動とは、本質的には社会秩序を取り戻そうとする草の根保守のバックラッシュ(揺り戻し)だったのではないか、そしてそれを支えていたのは総力戦大戦下を経て出現した冷戦の理論だったとする。すなわち、冷戦世界とは、それぞれの社会において秩序安定装置を機能させ続けるための壮大な言説的装置、想像上の「現実」だったとする。故に、冷戦の参加者は各国の指導者層だけでなく、社会における秩序維持と調査形成に意識的また無意識的に関与していた世界各地の何百万もの普通の人びとも、その参加者の列に含まれていた(同書、317頁)
まず、本書を読んだ感想としては、顧みてみれば自身などは、戦後の「満洲」でさえなかなか飛び出せずに、中国でさえ接続する事が難しく、ましてやこの本のように日本やアメリカ社会との共通点と差異というようなことをほとんど考えたことすらなかった人間としては、何というか自分の視野の狭さを思いしらされた。そして、この本が個別史とグローバル史をどのようにつなげられるについて、非常に興味深い事例を多く出していることは間違いない。もちろんこれがうまくつながっているのか、或いは繋がっていないのかについては、今後も多くの議論がなされるだろうし、中国近現代史の人間も参加しなければならないと思う。そうしてこそ、グローバルな冷戦という現象を理解することができると思う。
しかし、第九章の「鎮圧反革命運動」(以下、「鎮反」)を取り扱ったところは、違和感があったのも事実である。著者は、「鎮反」は過去との連続性があり、一連の社会的規範を掲げているのを重視している。例えば、不潔に対する清潔さ、無秩序に対する団結と調和、だらしなさにたいする正確さ、また退廃−或いは腐敗・汚職行為に−対する潔癖さ、という具合である(284頁)。ここで1930年代の国民党の「新生活運動」との共通点すら見えるとする(これは率直言うとやや飛躍した感じはもったが)。そして、こうした課題の核心にあったのは、近代化を成し遂げようとする取り組みだった、とする(285頁)とある。無論、近代化というワードはもちろん、近現代中国にとって大きな課題であった。しかし、他の国の事象では余り出てこず、ここで特に強調されている印象を持ったのも事実である。ここで一つ疑問となるのは近代が課題となるのは中国だけで他の国はならなかったのかという点である。例えば、アメリカやイギリス、日本、フィリピン、台湾等ではということが疑問に思った。
もう一つ、「鎮反」において「社会の敵」とされた「一貫道」などの有力宗教組織も扱われている(287頁)
しかし、「一貫道」については、「鎮反」の前にすでに社会から排除するようなキャンペーンが既に大々的に行われている。この事はどう考えるべきなのかというのは、率直に思った。昔に読んだ『東北日報』の「一貫道」粛清キャンペーンは、「鎮反」や「朝鮮戦争」の前の1949年にすでに大々的に行われているようにも思われる。以下、個人的にメモした記事のタイトルを列挙する。
1949年7月13号
「国特操纵封建会门进行各种破坏活动 大家应时刻严防」
「揭露和打击国民党特务利用一贯道等会门捣乱进行破坏」
1949年8月14日 「反动会首作恶多端 勾结匪特破坏生产」
1949年8月21日「逮捕一贯道反动匪首 并展开群众宣传工作」
1949年8月28日 顾雷「一贯道的丑恶面目」
1949年9月四日「受骗群众纷纷退出会门检举反动会头」
じゃあ、なぜその前の内戦期にはあまり「一貫道」の排除が行われず、この時期になって急に排除が行われているのかという至極当然の疑問にはまだ僕は十分に答えられない(仮説はあるが)。そうすると、恐らく朝鮮戦争の勃発前からの流れと勃発後の激しく大規模化する「鎮反」化の連続性と非連続性を明らかにすることがまだ求められるのではないかとも思った。
いろいろつらつらと書いたが、本書はローカル史とグローバル史とを組み合わせ、まさに総力戦後の世界を描かんとする全体史の試みであり、この時期に関心のあるひとびとの必読書であることは間違いないだろう。